楽器
お気に入りの楽器たち
| Bass | Fender Jazz BassCrafted in Japan / Bacchus Fretless / Schecter Bass-Guitar / Greco 8-string / Steinberger XL-2 |
| Keyboards | KORG KROME / KORG Prologue / iRig Keys 2 Pro / Roland PK-5 |
| Tablet | iPad mini 5 |

 左端に見えているのが現在のメインベース、カナダ旅行の後に(衝動買いで)手に入れたFender Jazz Bass - Geddy Lee Modelで安心の1本です。かたや右端のGrecoの8弦は相当に握力を必要とするため、1曲終わると左手がつりそうになるほど。ヘッドヘヴィーで少々バランスが悪いのもつらいところですが、独特のマイルドな複音が出ます。左隣のSchecterのダブルネックは京都在住時に特注したものですが、いまだこれを活躍させられるだけの技量がないのが残念。これらの手前のJazz BassタイプはBacchusのエントリーモデルですが、前々からフレットレスを弾いてみたいと思っていたので激安価格に惹かれて購入しました。トーンを絞ってブリッジ寄りを弾くと雰囲気が出ます。
左端に見えているのが現在のメインベース、カナダ旅行の後に(衝動買いで)手に入れたFender Jazz Bass - Geddy Lee Modelで安心の1本です。かたや右端のGrecoの8弦は相当に握力を必要とするため、1曲終わると左手がつりそうになるほど。ヘッドヘヴィーで少々バランスが悪いのもつらいところですが、独特のマイルドな複音が出ます。左隣のSchecterのダブルネックは京都在住時に特注したものですが、いまだこれを活躍させられるだけの技量がないのが残念。これらの手前のJazz BassタイプはBacchusのエントリーモデルですが、前々からフレットレスを弾いてみたいと思っていたので激安価格に惹かれて購入しました。トーンを絞ってブリッジ寄りを弾くと雰囲気が出ます。
書斎に遁世しているヘッドレスのSteinbergerはパワーがあってノイズが少ないのが特徴で、ネックも丸みがあるものの細くて弾きやすく、指板がはっきりえぐれるほど弾き込みましたが、あるとき故障したブリッジを純正品以外のものに交換したら音が変わってしまいがっくり。今では気が向いたときに指のなまりを防ぐために手にとるくらいになってしまいました。
キーボード類はたしなみ程度、iPadには音源アプリを搭載してMidiキーボード及びフットペダルと繋いでおり、iPhoneのGarageBandを録音に利用しています。
お気に入りのベーシストたち
Chris Squire
イギリスの大御所プログレッシブロックバンド、Yesのベーシストにして人事部長。愛機Rickenbacker4001で革新的なベースラインとサウンドを産み出し続け、他の追随を許さない個性的なベーシストとして知られます。Yesは数多くのメンバーチェンジを経ていますが、最も代表的なメンバー構成は、Jon Anderson(Vo)Chris Squire(B,Vo)Steve Howe(G,Vo)Rick Wakeman(Key)Bill Bruford(Ds)の5人です。

Chrisの演奏姿は何度も見ていますが、ご多分に漏れず体型が徐々に膨張していくのに比例して演奏のスピードもゆっくりになっていくのが残念。しかしRickenbackerのゴリゴリサウンドだけはいつまでも健在……だと思っていましたが、2014年11月の『こわれもの』『危機』再現ツアーが彼の姿を見た最後の機会となりました。〔2015/06/27逝去・行年67歳〕
 |
 |
 |
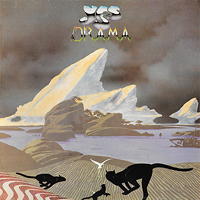 |
 |
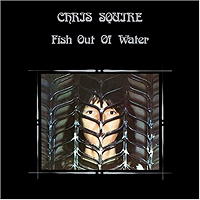 |
- 『Fragile』(1971)
- 意欲的にあれもこれもとアイデアを詰め込んだような作品ですが、Chrisのベースを知るためにはやはりこのアルバムの1曲目「Roundabout」を避けて通るわけにはいきません。
- 『Close to the Edge』(1972)
- 「プログレ」という枠を超えてロック史に燦然と輝く名盤。タイトルナンバーは20分近い大曲で、その後の大作主義の走りとなりました。つべこべ言わず、とにかく聞くべし。
- 『Relayer』(1974)
- Patrick Moraz(key)が参加した唯一の作品。「Sound Chaser」の疾走感は爽快、「To Be Over」のシンセサイザー・ソロが哀しくも超絶。
- 『Drama』(1980)
- Jon AndersonとRick Wakemanが抜けThe Bugglesの2人(Trevor Horn / Geoffrey Downes)が参加して制作された異色作。Yesファンの間では過小評価されることが多いようですが、私は好きです。
- 『90125』(1983)
- 「Owner of a Lonely Heart」が大ヒット。『Drama』が失敗して一時解散した後、ChrisとTrevor Rabin(G,Vo)を核にして再結成したYesの好アルバムです。「Our Song」と「Hearts」が個人的には気に入っています。
- 『Fish Out of Water』(1975)
- Chrisの初ソロ作品は、Bill BrufordやPatrick Morazらのサポートを得て、当時続々リリースされたYesのメンバーのソロ作の中でも最も充実した内容で好評を博しました。しかし、オープニング曲「Hold Out Your Hand」のあまりにかっこいいベースとプロモビデオでの振袖姿(YouTubeなどで見ることができます)のミスマッチには、誰もが呆然とします。
John Wetton
「栄光の」という冠詞がつくプログレッシブロックバンドKing Crimsonの1972年から74年までのベーシスト、というのが私にとっての彼です。その後のU.K.やAsiaを率いての活躍でも知られますが、ベーシストとして最高に輝き、天性のメロディセンスと自在なテクニックでリスナーを圧倒したのは、Bill Brufordとのリズムセクションが強力だったKing Crimson時代。以後の彼は次第にバンドの中でコンポーザー / ヴォーカリストとしての比重を高め、それとともにベースの魅力が薄れてしまったのが惜しまれます。それだけに、Steve Hackettのツアーで来日したときにサポートベーシストとして奔放にベースを操ってみせてくれたのは、彼のファンとしてとてもうれしいひとときでした。

Johnの演奏は、U.K.、Asia、ソロ、Steve Hackettのサポートなど何度も観ていますが、最後の来日は2015年4月のU.K.でのステージでした。〔2017/01/31逝去・行年67歳〕
 |
 |
 |
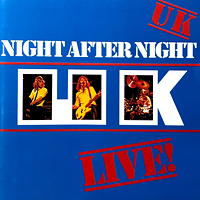 |
 |
 |
- 『Larks' Tongues in Aspic』(1973)
- John WettonとBill Brufordが加入した新生King Crimsonの最初のアルバム。中学生のときにこれを部室で聞かされてプログレにはまることになった因縁の(?)アルバムでもあります。邦題『太陽と戦慄』というのも秀逸。
- 『The Nightwatch』(1997)
- King Crimsonの絶頂期だった1973年11月23日のアムステルダムでのライブ。とてもインプロヴィゼーションとは信じられない「Starless and Bible Black」、叙情的なベースラインが美しい「Exiles」、破滅的なまでのスピード感に圧倒される「21st Century Schizoid Man」など、本質的にライブバンドである彼らの演奏を聴くことができます。
- 『Red』(1974)
- John Wettonの支配力が際立ちヘヴィメタリックな色合いも持つ作品。タイトルナンバー「Red」がそうした傾向をとりわけ色濃く示していますが、このアルバムをリリースした後、Robert Frippはバンドを解散させてしまいます。
- 『Night After Night』(1979)
- Johnの初めてのリーダーバンド、U.K.の日本でのライブ。私が観に行ったのは中野サンプラザでの初日で、Johnはもちろん、ヴァイオリンとキーボードのEddie Jobson、ドラムのTerry Bozzioのいずれもテクニシャンかつアイドル顔でかっこよかったのを覚えています。
- 『Asia』(1982)
- 全米大ヒットしたAsiaのデビューアルバム。結成時にメンバーリストを見て「えっ、あのリズムの悪いCarl Palmerとリズム隊を組むのか?」とJohnに同情しましたが、曲はいずれもドラマチックで捨て曲なし。産業ロックの記念碑的作品でもあります。
- 『Voice Mail』(1994)
- ベーシストというよりヴォーカリストとしてのソロ作品。歌詞の内容もよりパーソナルなものに。それでも気合の入った演奏が聴ける佳曲が並んでおり、彼のソロの中でもお勧めの1枚です。
Geddy Lee
カナダのハイテクロックグループ、Rushのベーシスト。Rushはセカンドアルバムをリリースした1975年以来、Geddy Lee(B,Key,Vo)、Alex Lifeson(G)、Neil Peart(Ds)の不動の3人組であり続けましたが、中でもリズムセクションの2人の超絶技巧は有名です。特にフロントを担当するGeddy Leeは右手人差し指ワンフィンガーで複雑なベースラインを弾きながらリードヴォーカルをこなす上に、曲中でベースとキーボードをスイッチしたり、ベースを弾きながらペダルでシンセサイザーをコントロールしたりするマルチプレイぶりが異彩を放っていました。ここで「いました」と過去形なのは、2020年にドラマーのNeil Peartが亡くなりバンドが終焉を迎えたからですが、Neilの行年も上記のChris SquireやJohn Wettonと同じ67歳。これは何かの因縁なのでしょうか?

Rushの最初で最後の来日である1984年のGrace under Pressureツアーで日本武道館のステージに立つGeddyを観られたのは幸福でしたが、以来待てど暮らせど来日の気配がない彼らに業を煮やし、2007年のSnakes and Arrowsツアーではトロントまで観に行ってしまいました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- 『2112』(1976)
- LPのA面全体を使った組曲「2112」が圧巻。彼らの記念碑的作品であり、長くRushファンにとっての「聖典」と呼ばれていました。
- 『Permanent Waves』(1980)
- Rushがそれまでの大作主義を離れてコンパクトかつモダンな曲づくりを指向するようになった作品。「The Spirit of Radio」「Freewill」などはライブの定番になりました。私がリアルタイムでRushを聴き始めたのはここからです。
- 『Moving Pictures』(1981)
- Rushの独自の音楽世界を確立した名作の誉れ高い作品。インストゥルメンタル「YYZ」での超絶技巧の応酬は手に汗を握ります。
- 『Grace Under Pressure』(1984)
- 「4人目のRush」と言われたプロデューサーTerry Brownと訣別して洗練されたシンセポップ方向へ舵を切った作品。彼らの1984年の来日公演は、本作のリリースに伴うツアーの一環でした。
- 『Power Windows』(1985)
- Geddy Leeのシンセサイザーへの傾倒が最高潮に達した時期の傑作。オープニング曲の「The Big Money」が極めてモダン。この辺りからRushはステージ上で自分たちの演奏だけで全ての音を再現することを断念するように……。
- 『My Favorite Headache』(2000)
- Neil Peartに相次いだ家族の不幸でRushが活動を休止していた間に制作されたGeddyのソロ作。基本的にスリーピースでのハードロックですが、随所にRushらしさが聴ける好盤です。Geddyがファルセットを使い始めたのも、たぶんこの作品から。